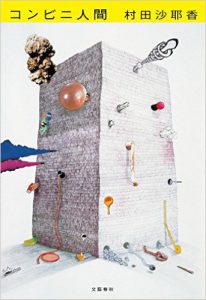
子どもの時の夏休みの課題図書から始まって、芥川賞とか直木賞とか本屋大賞とか「みんなが読むものは読みたくない」というポリシー(?)からはずれた久々の読書でした。
ちなみにネットで調べてみると、芥川賞は1998年の「日蝕」(平野啓一郎)以来、直木賞は99年の「王妃の離婚」(佐藤賢一)以来いっさい読んでいません。
読後の最初の思いは、「みんなが読むものは読みたくないという私のポリシーは、だれのコピーなんだろう」というものでした。
主人公の恵子は、この世の一般常識という不文律を自然に身に着ける能力の欠落している人。
素のままに行動すると、煩わしいことがたくさん起こってくる。
家族に心配される。
「なぜ普通に就職したり結婚したりしないの」といった彼女には答えようのない質問をされる。
しかし、学生時代に飛び込んだバイト先のコンビニで、彼女は自分が「本当にこの世に生まれた」と感じる。
完全にマニュアル化された世界。
マニュアル通りに動けばこの世界の一部品になれる。
彼女はさらに個人的生活にもマニュアル化を進めていきます。
この世の「異物」でなく「部品」であり続けるために。
同世代のコンビニの同僚のしゃべり方をコピーし、ファッションをコピーし、学生時代の友達と話をあわせ…「普通の30代独身女性の型」に自分を当てはめていきます。
物語は、このマニュアル世界から恵子がいったん引きずりだされ、再びそこへ戻っていくという単純なものです。
その過程で、恵子が抱く疑問。
この世の中は、恵子が学びえない一般常識というマニュアルに沿って展開しているだけではないか。
「みんな『普通の人間』という皮をかぶって、そのマニュアル通りに振る舞えばムラを追い出されることも、邪魔者扱いされることもない」。
そして、自分が「普通の人間」なのではなく、「コンビニ人間」なのだと意識する。
非常に深刻な心理小説でありながら、読後のあっけらかんとした「明るい」といってもよいような心持は、自己と世界の認識を深めた恵子を、読者としての私が受け入れられたという安堵感なのかもしれません。
神様は、私たちをそれぞれ違う形にお創りになりました。
しかしその私たちは個性豊かでありながら、互いに影響を与え合っている。
その中でできてきた不文律のマニュアルがある。
それは、時に別の目で眺めて、改訂しなくてはならない。
それを意識しないと、私たちは傲慢な自己中心主義に陥ってしまうかもしれません。
(Sr.斉藤雅代)
村田沙耶香著『コンビニ人間』 文藝春秋 (2016/7/27) 第155回芥川賞受賞作
